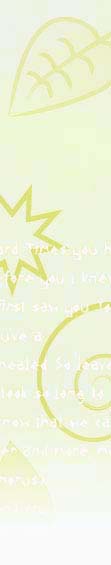
拝啓冬がその別れを惜しんでいるように寒い日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか。
先日はお宅に招待して頂き、あんなにも大人数で押しかけたにも関わらず、奥様のおいしい手料理までご馳走して頂き本当にありがとうございました。学生の学校離れ、教授の学生離れが進む中、自分の研究会の教授と奥様が本当に学生のことを思ってくれている事を幸せに思っています。
何やかやと御心労をわずらわせておりましたが、お蔭様で無事に卒業することができました。この僕も4月からはいよいよ社会人となります。長いようで短かった大学でも4年間を振り返ってみると、不思議と研究会での2年間のことばかり思い出します。これでもかと言うぐらいがんばった事が、自分自身の自信に繋がり、また最高の思い出にもなるという先生のお言葉がまさしくあてはまります。そしてそれは逆に言うと、それだけ1,2年生の頃は何もしていなかったということでしょう。
事実、僕は日吉キャンパスにはあまり行きませんでした。そんな僕が、脱落することなく、周りの友人たちに驚かれながらも研究会での2年間を無事に乗り切ることができたのは、先生の私達に対する熱意のお蔭だと僕は考えています。本当に、本当にありがとうございました。研究会も卒業という事にはなりますが、卒業式、園遊会では卒業することを全く実感できなかったのに、先生のお宅で先生のお言葉を頂いた時、自分が卒業することをはじめて実感するほど、先生は僕にとって大きな存在です。
どうか今後とも社会人の先輩として、ご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い致します。
末筆になりましたが、くれぐれもお体を大事になさって下さい。これからもお二人の益々のご健勝とご活躍をお祈りしています。 敬具
拝啓早春の候、日々お元気にご活躍のおもむき心よりお慶び申し上げます。
先日はお忙しい中お手紙を頂き、誠に有難うございました。大学を卒業するにあたり、先生からこのような貴重なお言葉を頂けることを非常に光栄に感じています。
私が環境問題に興味を持ったのは、小学生の頃でした。テレビや雑誌で頻繁に地球環境の異変が採り上げられ、子供ながらに人類の未来はいったいどうなるのか不安でした。しかし先生のゼミに入れて頂いて、研究を始めるまではこの問題の奥深さにはほとんど気づいていなかったと思います。
環境問題をとりまく状況は、非常に複雑で、企業、政府、消費者等が協力しないでは解決できないということや、各国政府や各企業の利害関係をも絡ませてしまう現状を知ることになりました。
大学生活の全てをこの問題の研究に注いだとしても、きっとそのほんの一部しか知ることができなかっただろうと思います。
それでも、ゼミの2年間において特に自動車廃棄物問題とエネルギー問題では、他のゼミ員に負けないくらい深く勉強したつもりです。これらについては論文を完成させた今でも興味を持っている問題ですし、一生忘れることはない問題だと思います。
自分たちが提言した内容が、たとえほんの一部でも社会で活用されるようなことがあれば、とても励みになります。
このように、1つのテーマを徹底的に追求し、完全に理解するまで妥協しないという、勉強に対する姿勢を教えて頂いたのは山口先生です。環境問題というテーマを取り上げ、その解決策を必死になって考えるということを何度も繰り返すことで、゛自分の頭で考えて何かを生み出す ゛という力が養われたような気がします。山口先生のご指導の下、常に自分に厳しく取り組んだ結果だと感じています。人生で最も「達成感」を味わえた2年間でした。 < 中 略 >
2年間という非常に短い期間でしたが、勉強面、社会人としての礼儀、その他数えきれない面でご指導を頂き、充実した大学生活を過ごすことができました。本当に有難うございました。先生の、゛遅刻するのは暇な人間である゛という言葉を胸に、一人の社会人として日本人の誇りを持って頑張っていきたいと思います。 また、合宿をはじめ、奥様にも大変お世話になりました。本当に感謝しています。
末筆ながら、皆様のご清祥を念じ申し上げます。 敬具
拝啓昨日は、お食事に呼んでいただき、大変ありがとうございました。御陰様でゼミとしての学生生活の楽しい思い出になりました。先生には、2年間いろいろご指導していただき、様々な面で学ぶことがあったと思っています。勉強の面ではもちろんのこと、それ以外にも社会人としての様々な教訓を教えていただいたことは これからの自分にとって大きな財産になっていくと思っています。
また、先生から頂いた「山口研究会5期卒業生に贈る言葉」における手紙の中で書かれていた日常の仕事にただとらわれず、常に一つ上の視点で物事を考える大切さの部分には大変勇気づけられました。以前から自分自身も社会人になったらこれからの日本、これからの世界がどうあるべきかという自分なりの視点をもつべきではないかと漠然とではありますが、考えていました。
そのため、企業でも成功された先生もその大切さを手紙で書かれていたのを読み、自分自身の考え方に勇気をもてるようになりました。4月からは新人として本当に学ぶことだらけで、忙しくなると思いますが、常に自分を見失わないためにも、常に一つ上の視点で物事を考えることを大切にしていきたいと思います。
今後も山口先生には、お世話になることがあるかもしれませんが、その時はよろしくお願い致します。最後になりましたが、山口先生の益々のご活躍を願っております。
敬具
拝啓日増しに春めき、桜の花も咲き始めましたが、山口先生には益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
早速ですが、先日は大変ありがたいお手紙をいただきながらお返事がおそくなってしまい申し訳ございませんでした。それというのも、昨日まで東京の弟の所へ滞在していたり、旅行へ出ていたりと不在をしていたからです。本当に申し訳ありませんでした。
ところで、卒業にあたってのお言葉ありがとうございます。しっかりと心に留めて社会へ出て行こうと思います。先生がおっしゃる通り、清華大学での発表の直後は、中国の学生のパワーに圧倒されてしまい、自信を喪失しかけました。しかし、私達も立派に発表を成し遂げたということを私の自信として、そして困難にぶつかった時にはやる気に満ちあふれていた発表前の自分を思い出して頑張っていこうと思っております。
最後になりましたが、先生には大変感謝しております。本当にありがとうございました。研究活動におけるアドバイスはもちろんのこと、「社会人たる心構え」も教えていただき、これらすべてが私の財産になりました。また、研究会を通してすばらしい仲間に出会えたことも大変幸せに思っております。ありがとうございました。
これからもご指導のほどよろしくお願いいたします。 敬具
拝啓陽春の候、山口先生にはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
先日は卒業に際してお心のこもったお言葉を頂戴いたしまして、ありがとうございました。また、この2年間先生には研究会での懇切丁寧なご指導を賜りまして本当にお世話になりました。
どんな論文でも必ず筋の通った論理とそれを裏付ける実証が必要であること。それは当然のことでありながら、未熟な私にとっては至難の技でした。しかし、大変ではありましたが、他の人と共同で論文を書くという作業は本当によい経験となりました。社会に出る前にこのような経験をさせて頂いたこと、本当に有難く感じております。卒論は今までと違い、自分一人でつくる論文でしたが、これまでの2年間、共同論文を書いた経験があってこそ、短期間にひとりで書くことができた、という気がします。
先生はいつも妥協せず、論理的な論文をわたしたちに常に求めて下さり、また社会人のルールについても折にふれわざわざ注意して下さいました。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。
末筆ながら、山口光恒先生の今後のますますのご発展、ご活躍とご健勝とをお祈りさせて頂きます。 敬具
拝啓桜の花も満開に咲く中、いかがお過ごしでしょうか。
昨日は、山口光恒研究会五期生の卒業にあたり盛大な食事会を開いて下さいまして、真にありがとうございます。先生や奥様に囲まれ同期と語り合う貴重な場となり、学生生活の最後にすばらしい思い出をつくることができました。また、先生の社会人とは何たるか、社会に出たらどのようなことが求められるのか、といった話は、4月から社会人となる私達にとって非常に身の引き締まる有意義なものでした。深くお礼申し上げます。
私のような未熟者が慶應義塾大学という名誉な大学を卒業することができたのも、先生の親身なご指導に依るものと思っております。思えば、山口研究会に入会したことは、私の大学生活を大きく変える出来事でした。
慶應大学に入学し、どのような生活が待っているのかと私は胸をはずませながら第一学年を迎えました。しかし、現実はそのような思いとは逆に、ただ何気なく日々を過ごすのみの生活を日吉キャンパスでは送っていました。そして、自分はなぜ大学に来ているのか、何をしに大学に入ったのか等真剣に考えた時期もありました。
そのような中、転機となったのが山口研究会のオープンゼミを見学したことでした。環境問題という非常に重要なテーマについて議論し、また先生の社会スタンダードのご指導を受けてみたいと思ったのがこの時でした。そして、山口研究会に入会することができたことまでは良かったのですが、まさか山口研究会で活動していくことがここまで大変なことであるとはその時は知りませんでした。
その事を初めて知ったのは、私が研究会で初めて発表したときでした。その時は、発表の仕方も全く分からず、自分でも何を言っているのか分からないといった状態でした。その時、先生は「皆の時間を無駄にするような発表をしてはいけない」とおっしゃりました。この言葉が全てを物語っていると思います。そして、私はこの研究会ではそれまでの半端な気持ちでは到底やっていくことができないということを実感しました。
そして、3年生の時で最も印象に残っている出来事が環境学生会議で発表したことです。
会議前の研究会での発表を見て、先生は「別の人が発表したほうがいい」とおっしゃいました。その言葉を聞いた私は、絶対先生に自分でも大丈夫だと認めてもらうために、自分が発表すると言い張りました。そして、自分としては会議の準備もやることはやったという気で、会議の前日、先生に私の発表を先生の研究室で見て頂きました。しかし、その時の私は、重要な点をほとんど理解しておらず、先生のお怒りを買いました。準備万端と思っていたのは、ただの思い上がりに過ぎなかったということを思い知らされました。そして、その日はただひたすら発表の練習を繰り返しました。あそこまで追いこまれ、我を失って取り組んだことは初めての経験でした。
不安をひきずりながら、私は会議を迎えました。私の出来は散々なものとなりました。会議での最初の発表者という重要な役割を担っていたのにも関わらずボロボロの出来であったこと、そして何よりも自分の甘さ、ふがいなさに沈んでいました。会議終了後、私は研究室に行くのが嫌で嫌で仕方ありませんでした。゛あわせる顔がない゛という表現があれほどあてはまったことはないと思います。そして、研究室で先生は「昨日より良かった」と私におっしゃいました。この時は、完全に自信をなくしている私の姿を見て、先生はこのようにおっしゃったのだと私は思いました。そして、ますます自分の情けなさを感じました。中国の時でも思わなかった「もう研究会をやめたい」という気持ちをあの頃は抱えていました。しかし、沈んでいる私を見て、支えてくれたのが同期の存在でした。同期の皆は、自分の気持ちを受け止めてくれました。そして、悩むよりも今後頑張っていく力に変えていけばいいという気持ちを転換させてくれました。
私は、この時初めて先生のおっしゃった「昨日よりよかった」という言葉の意味を本当の意味を理解できたと思いました。「次はもっといい発表ができるように、一生懸命になって取り組んでいくことが大切なんだ」というのが先生の言いたかったことなのではないか、そう前向きにとらえて頑張っていこうと思い、私は研究会にとどまることを決意しました。この時もし研究会を退会していたら、中国をはじめそれ以降の大変貴重な経験をすることができず、日吉時代のようなだらだらとした生活に戻ってしまっていたことと思います。そのようにならずに済んだのは、支えてくれた同期そして先生の言葉に依るものでした。
続いて、4年生の時の最も印象に残る出来事をあげるとしたらやはり、清華大学との環境会議でしょう。私にとっては、慶應環境学生会議の雪辱戦、そしてそれから1年間ゼミでやってきたことを先生に見せる最後の機会だと思っていました。ゼミで学んだことというのは、研究するのと、その研究したことを発表するのは大きく異なること、そしてその差を埋めるためにはロジックを通すことが最も重要であり、また自分に自信をもてるように一生懸命取り組むことが必要であるということです。会議本番、そして会議までの研究過程においてこのことを意識しながら取り組んだ結果、自分でも満足のいく発表をすることができました。そして、発表終了後の先生の「よくやった、いい発表だった」という言葉、そして先生の満足そうな顔は一生忘れません。この時初めて、1年前のリベンジが果たせたのではないかと思いました。
ゼミでは、先ほどあげたことの他、数多くの事を学ぶことが出来ました。私の大学生活を有意義なものとしてくれたのがゼミであることは間違いありません。それも、先生の学生を思うが故の厳しさに依るものだと思っております。ゼミでの経験を今後、社会に出た時に必ず活かしてみせます。そして、先生に良い報告ができるよう立派な社会人になれるように、日々頑張っていきたいと思います。2年間本当にありがとうございました。そして、またお会いできることを楽しみにしております。 敬具
このページ及びこのページからリンクされているコンテンツはすべてフリーですが、著作権は山口研究会にあります。
CopyRight by Yamaguchi Seminar