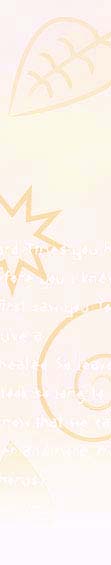廃棄物問題を「拡大生産者責任」を中心に研究している。日本でも容器包装、家電にこの思想が取り入れられたが、現在廃自動車につき法律制定の動きがある。この内容をどうしたらよいかなどを研究している。
ISO環境管理規格(14000シリーズ)については規格作りの国際交
渉に参加してきた経験から、日本企業の対応につき研究している。
募集人員:約16名
B日程の実施は状況による
選考試験:未定 昨年は課題図書の感想文と面接
選考基準
日吉でどれだけしっかり勉強してきたかを見る。表面的な成績ではない。
ゼミ代表から見た山口ゼミ
山口ゼミ研究会に入った私の感想として、まず挙げられるのは、環境問題に対して見識を深められるということです。これは、最大限の努力と時間をゼミに費やすこと、山口先生がゼミ生の研究に対して熱心に指導をして下さるからです。
ゼミは基本的に週一回となっています。これは、他のゼミに比べて多いとは決して言えません。しかし、この週一回のゼミでは、日頃研究していることを、ゼミ員の前で発表し、議論し、お互いの理解、知識を深める場であるため、その発表に際してはそのテーマについて最大限の努力を研究に費やした上で発表しなければなりません。そのため、ゼミ活動は週一回となっていますが、発表には準備期間を要するため、週一回だけの活動とは決して言えず、ゼミの活動に相当の時間を費やすことになると言っても過言ではないように思えます。
日頃山口先生は、何事をするにもメリハリが大切だと仰っており、ゼミ以外に個人的に取り組んでいることがあっても、自分でメリハリがつけられる人にはゼミ活動は苦にはならないように思えます。しかし注意としては、ゼミ活動と個人的に取り組んでいる活動が重なったときは、ゼミを優先しなくてはいけないので、個人的な活動を重視したい人には、ゼミ活動が障害になりかねないのでゼミ選びのときにはよく考慮してください。
発表においては、先生からいろいろなコメントを頂けます。先生ご自身が国際会議、政府の委員会などに出て活躍されていることから、国内、国外を問わず、どのような議論が現場で行われているのか、学生が研究することでは得られないような知識、情報を与えてくださります。先生は日頃会議や研究でかなり忙しいのですが、ゼミの時間以外にも快くゼミ員の研究の相談にのってくださります。
また、先生はゼミ員を社会人として扱いますので、ゼミ員は社会人としての礼節まで多岐に渡り求められることになります。ゼミ員は環境問題の見識を深めるだけでなく、一人の社会人としても成長できると言えるでしょう。
さて、実際の研究内容についてですが、ひとつの特徴として、英語で書かれた資料を読む機会が多いということがいえます。環境問題は国際的に研究されている分野のため、他国の資料を英語で読む機会が多いということは、環境問題を研究する上での特徴といえるかもしれません。実際、ゼミ活動において他国の資料読むことは多く、原文を読んだことで新たな発見が多いことは事実です。
その他、研究を進めるにあたり、企業や省庁にヒアリングをすることが多いことも特徴と言えます。現場を見に行くということは、何を研究するにしても大切なことだと思いますが、環境問題を研究する場合はとりわけ、現場を見て、現場の人の話しを聞くことが大切なのでヒアリングは大切な活動といえるでしょう。
日頃の研究を発表する大きなイベントとして、山口研究会では、三年生は11月に同志社大学とインゼミ、12月には環境学生会議において発表、4年生は中国で清華大学の大学院生とインゼミを行います。他大学の学生や、慶応内の他ゼミの学生の前で発表、議論を通じて得られるものは、日頃のゼミ活動とは違う発見、刺激があり、インゼミはゼミ活動におけるひとつの醍醐味だと思います。私は同志社大学、清華大学とのインゼミにおいて発表をしましたが、インゼミを通じて、研究が深まるばかりではなく、同志社大学、清華大学の学生と勉強を離れたところでの交流により仲が良くなり、そこで得られたものは大きく、とても貴重な経験ができました。環境問題に対し同じ様に深い問題意識を持っている他大学、他ゼミの学生と交流を深められる機会がある、これも山口ゼミの特徴といっていいと思います。
最後に、私が今年の四月から山口ゼミに所属してみて、山口ゼミのゼミ員に求められているものは何なのだろうか、と私なりに考えてみると、それは何よりやる気だと思います。山口先生は、ゼミ員に、今までで一番勉強したと言えるようにゼミに取り組み、自分はこれだけやれるという自信をつけて、慶應に入って本当に良かったと思いながら慶應大学を卒業して欲しいと仰っています。山口先生は教育熱心ですし、ゼミには環境問題に関心を持っている仲間と一緒に研究をしていく環境が整えられています。自由な時間がたくさん与えられている大学生活で、その時間を自分の関心のある環境問題について見識を深めるために費やしたい、そんなやる気のある人に山口ゼミをお薦めします。簡単ですが、以上が私の視点から見た山口ゼミでした。かなり個人的な意見なので、偏りもあると思いますが、みなさんのゼミ選びのお役に立てれば幸いです。
外ゼミ代表 瀬川 晋
学生からみた先生
山口教授はゼミ生の研究活動にたいへん協力的で、同時にゼミ生の人間としての成長にも気を配ってらっしゃる方です。学業面では単なる知識教養の習得だけでなく論理的思考能力や創造力等も重視されているので、時には学生の研究に厳しい指摘をなさいますが、多くの国際・国内機関の役員を務め多忙さを極める中、様々な情報や助言を提供してくださるため学生からの信頼は厚いものがあります。また学業を離れれば、飲み会や伊豆合宿などで学生と積極的に交流を図られるので、公私にわたり学生をサポートしてくださいます。先生は上記のような能力や知識、礼儀作法や思いやりの心など、総合的に人間を磨くために大事なこと、社会人として生きていく上で必要なものを重んじられています。教授は、国際会議に出席される場合を除き、毎回ゼミには出席されます。
活動内容
- 本ゼミ 毎週水曜日4・5限
本年度の前期は、三年生は廃棄物問題を中心に研究し、OECDのEPRガイダンスマニュアルの輪読、発表をしました。四年生は地球温暖化問題を中心に研究し、IPCC地球温暖化レポートなどの地球温暖化に関する様々なトピック・文献について輪読・発表をしました。
- サブゼミは行われていません。
- パートゼミ
三年生: 「自動車廃棄物班」 「容器包装リサイクル班」 「家電リサイクル班」 「ゼロエミッション班」
の四つのパートに別れ研究しています。
四年生: 「地球温暖化班」 「エネルギー班」 「水資源班」
の三つのパートに分かれて研究しています。
- 三田祭
三田祭期間中は3年生が各パートの研究の成果を一般公開し展示します。当研究会の具体的な研究内容を知るいい機会ですので、ぜひご来場下さい。
- インゼミ
三年生
●同志社大学群島研究会とのインゼミ(京都、11月上旬開催予定)
●慶應義塾大学内の環境問題を研究するゼミとの環境学生会議(12月上旬開催予定)
四年生
●中国清華大学のウェイ教授の研究会とのインゼミ(三田祭期間中)
- 合宿
●伊豆合宿―教授の別荘に宿泊し伊豆の海を満喫します。勉強は一切しません。(任意)
●ゼミ合宿(那須高原)
三年生
春学期以降のパートゼミのまとめとして、各パート発表、議論
OECD・EPRガイダンスマニュアルの発表、議論
四年生
中国清華大学とのインゼミに向けての中間発表、議論。
●夏休み―ゼミ合宿に向けてパートごとに研究・フィールドワーク等。
授業
水曜日2限 地球環境問題と企業 山口光恒
木曜日1限 環境経済論 細田衛士教授 大沼あゆみ教授
木曜日4限 地球環境経済論 細田衛士教授 寺出道雄教授
以上の三つの授業を必修としています。その他にも、推奨されている授業がいくつかあります。
経費
合宿、インゼミにかかる費用以外はゼミ員が書く論文の原稿料で賄っています。不足する場合は、必要に応じて徴収します。
選考試験対策
課題図書をよく読み、そのすべてを会得できるように努力すること。しかし、それよりもまず、日吉で真剣に勉強することや日頃から環境問題に関心を持っていることが重要です。
質問等のお問い合わせについて
山口ゼミに関する質問がある方は、些細な事でも遠慮せずに下記の連絡先まで問い合わせてください。
- 来年度の研究会の入会審査について
当研究会は、他学部からの学生も受け入れています。
- 本年度の研究会において、現在の3年生、4年生の中に他学部からの受講者数。
3年生 3人
4年生 0人
- 他学部から受講しようとする学生に対しての教授・学生からのアドバイス。
山口教授より
研究会への入会を希望する学生は教授のホームページ及び当研究会のホームページの
入ゼミに関する注意を良く読み内容を了解した上で応募して下さい。
教授ホームページ:http://www.econ.keio.ac.jp/staff/myamagu/
山口研究会入ゼミ係より
当研究会では、環境問題、特に、地球温暖化問題、廃棄物問題について研究していま
す。当研究会では、環境問題を多角的な視点で捉え、幅広いアプローチから実現可能な政策・解決策の模索をします。環境問題の解決策模索には、あらゆる分野からの分析が必要になります。当研究会では、経済学的な視点だけでなく、法律や政治の視点も重要視しています。例えば、公平性を考える際には、法律の視点、京都議定書などを考える際には、政治の視点が必要となります。
当研究会では、他学部学生も、経済学部学生と隔てることなく、受け入れています。環境問題に関心があり、やる気のある方をお待ちしています。
入ゼミ説明会結果報告
2002度第一回入ゼミ説明会(2001年6月23日) 参加者 40名(男24名 女16名)
2002度第二回入ゼミ説明会(2001年11月10日) 参加者 76名(男57名 女19名)
多くのご参加ありがとうございました。
入ゼミ資料