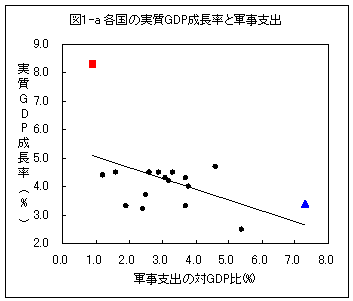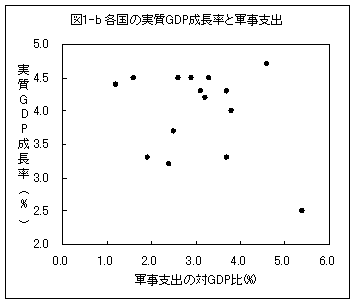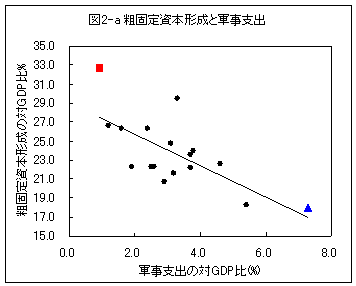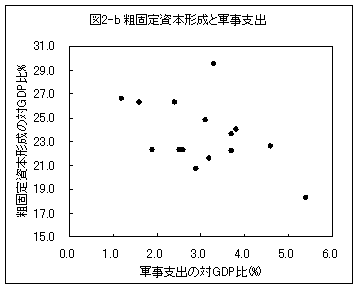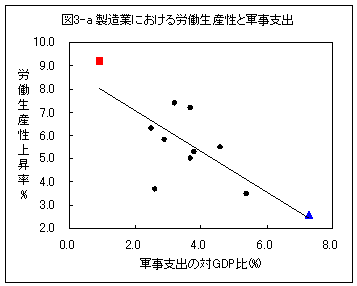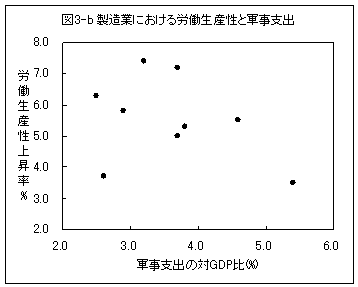戦後日本の経済成長の性格
延近 充
(この論文は,慶應義塾大学通信教育部 『三色旗』1996年4月号 「特集 戦後五十年をふりかえる」
に掲載した論文に加筆・修正したものです。)
1. 戦後50年=日本の「経済大国」化
1945年8月の敗戦=15年戦争の終了後,約6年8カ月という長期の占領を経て,52年4月に日本は独立を回復する。日本経済は戦争によって極度に荒廃していたが,初期占領政策が日本の非軍事化およびそのために必要な民主化を目的としていたのに対して,冷戦の激化とアジアへの拡大のもとで占領政策は日本を反共のアジアにおける拠点とするために資本主義的復興をめざす方向に変更された。占領下での諸改革と経済復興政策によって,独立回復時にはすでに農業・工業生産,実質国民総生産等の主要経済指標は戦前水準(1934〜36年平均)を回復していた。その後,55年頃から約15年にわたって世界にも例を見ない急速な経済成長が出現し,日本は「経済大国」となっていったのである。
この間,実質国民総生産(GNP)は,年平均10%を超える成長によって4倍強となり,60年代後半には資本主義世界第2位となった。産業構造は,石油化学,電機,自動車などの新しい産業が次々に創出され急成長を遂げて重化学工業化がすすみ,輸出構造においても重化学工業化が進展して60年代半ばには貿易収支は黒字基調に転換した。これにともなって就業構造も大きく変化し,55年には全就業者の4割強を占めていた第1次産業の就業者は,70年には2割弱に減少する一方,第2次産業の就業者は24%から34%へ増加,第3次産業の就業者は36%から47%へと増加する。
こうした変化は,農村から都市への人口の大移動と大家族から核家族への家族構成の急速な変化も引き起こした。
また国民生活においても,家庭電化製品(洗濯機,冷蔵庫,掃除機,テレビ等)や自家用乗用車の急速な普及など,消費革命と呼ばれる消費・生活様式の一大変化が起こった。
70年代に入って,ニクソン新政策の発表によって金とドルとの交換が停止され外国為替がスミソニアン体制を経て変動相場制に移行するなかで,日本政府・日本銀行は輸出維持と国内景気刺激のために大規模なドル買い介入・調整インフレーションと列島改造政策をとった。
これによって設備投資が刺激されるとともにインフレーションが加速し,投機的取引を促進して土地価格や諸商品価格が暴騰していったことから,73年半ばに総需要抑制政策をとることを余儀なくされて約15年にわたる高度成長は終了する。
さらに原油価格の大幅引上げ(第1次石油危機)によって, 74年には戦後初めてGNPはマイナス成長となり,70年代を通じて低成長と物価上昇とが併存する状態が続くことになる。
当時の資本主義諸国に共通してみられた,いわゆるスタグフレーションであるが,これはたんに低成長と物価上昇が並存する状態が続く現象それ自体が問題なのではない。
第1に,60年代の景気拡大によって形成された過剰生産能力と過剰貨幣資本の存在のもとで,これらを一挙に解消するような設備投資を誘発するだけの新生産部門の形成や革新的新生産方法の開発がないために,独占段階固有の停滞基調が顕在化し支配していること。
第2に,その状態のもとで国家が通貨膨張や財政支出拡大による成長刺激政策をとれば本格的な景気拡大が実現しないまま物価上昇が加速し,逆に物価上昇を抑制しようとすれば景気がさらに後退するという状態に陥っていること。
つまり,戦後の資本主義経済の復興と成長を支えた条件が失われたもとで,景気停滞と物価の持続的上昇の両方を同時に解決する手段がなくなった事態として捉える必要がある。
もっとも,高度成長期に比べれば低成長になったとはいえ,他の先進資本主義諸国の実質経済成長率が2%程度であるのに対して,日本は円高が進行する中でも徹底した減量経営と輸出拡大によって5%前後の成長率を維持していた。70年代末の第2次石油危機によって一時期成長率は低下するが,80年代に入ると急速に回復し,86年の円高不況後のいわゆるバブル景気の時期には5%台の成長率を回復することになる。
こうして1950年に アメリカの4%にも満たなかったGNPは,高度成長の終わり頃にはアメリカの20%を超え,80年代末には58.7%(国内総生産GDP)に達するまでになったのである
)。
2. 経済成長と軍事支出
なぜ戦争直後の荒廃からこれほど急速に「経済大国」化が実現できたのだろうか。戦後の日本経済の復興と高度成長のメカニズム自体を分析するのは本稿の課題ではないので,ここでは,アメリカ経済の衰退と日本の急速な経済成長とを対比して,その原因を軍事力と軍事支出の大小に求める考え方を検討してみよう。
軍事と経済との関係をどのように考えるかという問題は,アダム・スミス以来の問題,いわば経済学の誕生以来の理論問題である。軍隊は,どのような理由づけがなされようとも本質的に殺戮と破壊のために存在しているのであって,生産や消費に利用されるものではない。したがって,軍事支出や軍需品の生産は,社会的再生産にとっては資源と労働力の浪費であって何の富も生み出さない。このこと自体には議論の余地はない。
しかし,第2次世界大戦にともなう巨額の軍需がアメリカ経済を30年代の長期不況から劇的に回復させ空前の経済的繁栄をもたらしたように,条件しだいでは軍事支出は経済成長を刺激する効果ももっている。また,第2次世界大戦や冷戦のなかで軍事研究開発に関連して生まれた新技術が,軍事以外の分野に応用されたことにより産業を発展させ国民生活を豊かにしたという考え方もある。どんな場合にも軍事支出や軍需生産は経済に悪影響を及ぼすのかということになると,問題はそう単純ではなくなるのである。
この問題に理論的に接近するのではなく,戦後の資本主義諸国の軍事支出と経済実績を比較し両者の間の相関関係を抽出することによって接近しようという試みがある。その代表的なものとして,R.ディグラスの分析結果のグラフを掲げておこう。
彼は,1983年の著書(1)のなかでOECD諸国のうち17カ国の経済統計の分析から,軍事支出の大きさと経済成長率,生産性上昇率,設備投資(2)等の経済実績との間には逆相関関係があり,軍事支出は経済に悪影響を与える,したがって巨額の軍事支出がアメリカ経済を衰退させた主要な原因であると結論づけている。
同様の考え方は 日本の研究者にもみられる。例えば菊本義治氏は「憲法による『歯止め』によって,日本の軍事支出が対GNP比1%の水準にとどまり,軍事支出の割合が他の先進資本主義諸国に比べて低かったのである。それが,高成長の重要な原因であった」(3)と述べている。
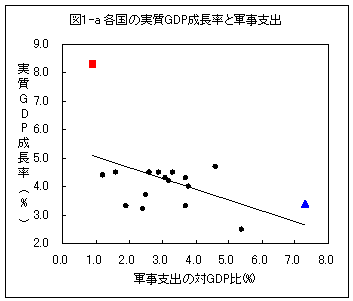 |
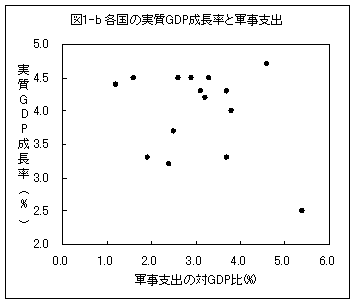 |
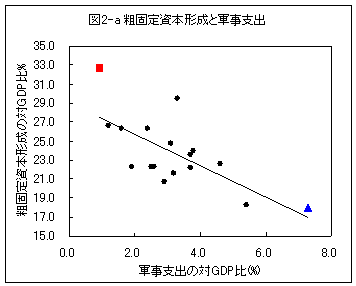 |
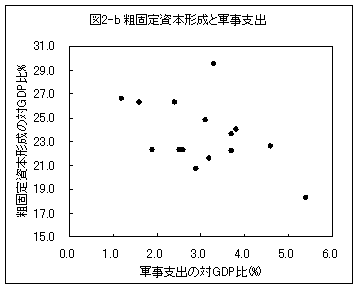 |
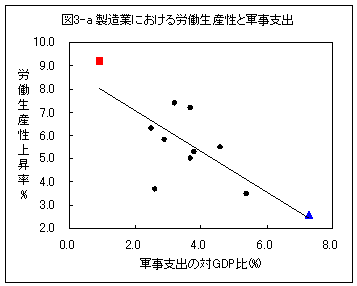 |
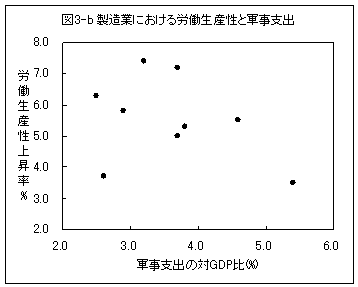 |
図はすべてRobert W. DeGrasse Jr.Military Expansion Economic Decline New York,1983, p.186, Table B.1より作成。
17カ国は,Australia,Austria,Belgium,Canada,Denmark,Finland,France,Germany,Italy,Japan,Netherlands,New
Zealand,Norway,Sweden,Switzerland,United kingdom,United Statesで,生産性上昇率のデータはAustralia,Austria,Finland,New
Zealand,Norway,Switzerlandの6カ国が入手不能である。
図1-a,2-a,3-aの赤色の四角のマーカーは日本,青色の三角のマーカーはアメリカである。
図1-b,2-b,3-bは,日本とアメリカを除いてグラフにしたものである。 |
たしかに,上の2つの図では,近似線が右下がりであることからそれぞれの2つの要素間に逆相関の関係があることが推測される。相関係数を計算すると,実質GDP成長率と軍事支出は-0.49,労働生産性と軍事支出は-0.76である。しかし,統計的な相関関係の存在は必ずしも因果関係の存在を示すものではない。したがって問題はこうした分析結果から背後にある関係をどう読みとるかである。
上の図1-a,2-a,3-aでは,近似線が右下がりであることからそれぞれの2つの要素間に逆相関の関係があることが推測される。相関係数を計算すると,それぞれ,-0.49,-0.69,-0.76である。
しかし,図からも容易に推測できることだが,日本とアメリカはそれぞれグラフ上の左上と右下の対照的で他の諸国とはかなり離れた位置にあり,この両国の値が全体の相関関係に大きな影響を与えていることが推測される。そこで,この両国のデータを除いて同様のグラフとしたのが図1-b,2-b,3-bである。この図を見れば,2つの要素間に明確な逆相関の関係があるとは読み取り難いであろう。実際,相関係数は両国を除いた場合,-0.28,-0.49,-0.35と小さくなって,明確な逆相関は見られなくなるのである(4)。
日米両国の値を含めれば軍事支出と経済のパフォーマンスには逆相関が見られるが,両国の値を除外すれば明確な逆相関は見られなくなるということは,統計的な事実の観察を超えて,日米両国の値が相互に独立的で無関係あるかどうかの検討をしなければならないということである。この検討なしに,軍事支出が少ないことが日本の高度成長の原因であるとか日本の高度成長が軍事とは無関係に実現したといった結論を導き出すのは方法的に誤っているのである。
実は,戦後の日本経済の急速な復興と成長は,アメリカの冷戦・軍事戦略に規定された恒常的な軍事力増強・軍事支出増大と深い関係をもっているのであって(5),このことを無視して戦後日本の経済成長の性格を理解することはできないのである。他方でアメリカ経済の衰退は日本の急速な経済成長によって促進された面をもっているのである(6)。
以下では,この関係を(a)占領期,(b)朝鮮戦争期,(c)ベトナム戦争期,(d)1980年代の4つの時期についてみていくが,戦後の日本経済の本格的な分析は本稿の課題ではないので,以下では要点の指摘にとどめる。
3. 戦後日本の経済成長の諸要因
(a)占領期
アメリカの初期の対日占領政策の目的は,日本の軍事力とその基盤の徹底 的な破壊にあり「民主化」政策はその目的に必要なかぎりでの政策であった。しかし,ヨーロッパでの冷戦が激化し中国の内戦によってアジア情勢も緊迫化してくると,占領政策は日本をアジアにおける「反共の防壁」・「反共の工場」として復興させるためのものになる。過度経済力集中排除法施行の緩和や公務員のスト権剥奪,日本政府への経済復興政策の指示,ドッジ・ラインの実施等である。
さらに1949年秋のソ連の原爆実験成功と中華人民共和国の成立によって対ソ・対中「封じ込め」政策における日本の軍事的・経済的重要性はいっそう増大した。こうしてアメリカの意図のもとに反共の拠点としての日本の復興が進められたのであって,国民の立場にたって国民生活を豊かにするための理念に基づく復興ではなかった。
(b)朝鮮戦争期
朝鮮戦争は冷戦の熱戦への転化を意味するが,この時期に日本の再軍備が開始され,また対日平和条約・日米安保条約の同時調印によって米軍駐留が恒久化することになった。米軍の軍事行動によるいわゆる朝鮮特需は,日本経済をドッジ不況から急速に回復させるとともに,復興の基盤的産業の合理化・生産拡大に大きな役割を果たした。日本はアメリカの軍事体制に組み込まれることを積極的に容認しそれと引き換えに経済発展のための有利な条件を獲得し,その後の高度成長の基盤がつくられていったのである。
(c)ベトナム戦争期
1960年代前半には高度成長は中断し不況に入っていたが,65年のアメリカのベトナム戦争への本格介入は,日本経済にそれまで以上の急速な高度成長の再現をもたらした。急増したベトナム周辺諸国へのアメリカの軍事支出と経済援助によってこれら諸国への日本からの輸出は激増した。アメリカ国内でも軍事支出の急増は景気を過熱させ,これは需要の増大とインフレによる国際競争力の低下によって,日本の対米輸出を激増させることになった。
こうした輸出の激増は設備投資の群生を誘発し,これによる生産力上昇が国際競争力を強化してまた輸出の増大をもたらすという循環により,輸出の増大を成長の不可欠の要素とする再生産構造が形成されていったのである。この結果,日本は「経済大国」化する一方,アメリカ経済は相対的に衰退し繊維・鉄鋼以降の日米貿易摩擦が始まることになる。日本経済の復興と成長は,冷戦体制のもとで資本主義体制の強化のためにアメリカの意図したものであり,それは見事に成功するのであるが,日本の高度成長はアメリカの意図を超えて展開し,逆にアメリカ経済を侵蝕することになったのである。
(d)1980年代
レーガン政権は「強いアメリカ」の再建をスローガンに軍事力大増強と経済の活性化のための諸政策を実行していくが,周知のようにこれらは財政赤字の急増とドル高をもたらした。これによって日本の対米輸出は急増し,日本経済は70年代末の不況から急速に回復するが,日米貿易摩擦は一層深刻化していった。80年代の日本の経済成長はレーガン軍拡によって可能となったともいえ,これは同時にアメリカの「双子の赤字」の深刻化と国際経済の混乱をもたらしたのである。
4. 戦後50年=日本の「経済大国」化がもたらしたもの
ところで,こうした急速な経済成長は,国民の大多数に年々生活が「豊か」になる実感を与えるとともに,経済成長こそが「豊かさ」をもたらすという意識,他者との競争のなかで利潤追求と物質的消費欲求を最高の行動基準とする意識(利潤・消費至上主義ともい うべき意識)を定着させていった。
この意識とそれに基づく行動は,いわば資本主義的競争社会の原理を極限まで純化して体現したものともいえ,戦後日本の社会の歪みを根底で規定しているのではないだろうか。いくつか例をあげてみよう。
占領下での民主化や高度成長期の就業構造の変化によって,地主や資本家といった伝統的な階級や半封建的家制度,共同体的地域社会は解体していったが,これに代わって巨大企業の社員や高級官僚,医師・弁護士等の自由業者等を上層とする所得や労働条件・社会的地位等を軸とするピラミッド型の新しい階層構造を生み出していった。
この階層構造は新しく生まれただけに流動的であり,上層に帰属するための主要な要件が学歴となったが,教育の機会均等は一応保証されているため大衆の上昇志向は一定程度実現され,平等社会という幻想・現状肯定的な中流意識と学歴至上主義(受験戦争体制)が生み出された。もっとも,高額の教育費を負担できる高所得者の子供ほど高学歴を取得するのに有利になるため,階層の流動性と機会の平等性は急速に失われていく。
また,数度にわたる土地・住宅価格の高騰は,土地・住宅を居住のためでなく所得と資産を増大させる利殖の手段として利用できる者とできない者との間に格差をつくりだしていった。
また,企業の利潤追求のための行動は高度成長の推進力であったと同時に土地・住宅問題,生活環境の悪化,公害問題等の深刻な社会問題を生み出していった。しかし,新しい階層構造の上層に帰属することが高所得と消費欲求を満足させる条件となるところでは,他者や社会全体の不利益を顧みないことが競争のなかで勝者となり,上層への帰属といっそうの上昇の手段となっていくのである。
こうして高齢者,病人や障害者,被差別国民や在日外国人等の社会的弱者の問題は軽視あるいは無視され,むしろ上層階層の(上層階層といえども 定年退職や公害・交通事故被害等によって容易に弱者へ転落しうるにもかかわらず)差別・特権意識が強化されていった。
さらに,高度成長期に本格化しはじめたアジアへの企業進出は,戦争責任と戦後処理を曖昧にしたままで,突出した経済力と戦後賠償にかわる紐付き経済援助を手段とし利潤・消費至上主義に基づいて実行された。そこでは,アジアに対する差別的優越感や特権意識を背景として,また海外での企業活動においては労働条件や公害規制その他の日本の国内法が適用されないことから,日本国内ではとうてい容認されないような劣悪な労働条件,環境破壊や現地の支配階級との癒着,買春等の社会問題を引き起こすことになった。15年戦争中の軍事的侵略との差は大きいといえるだろうか。
戦後50年の日本の経済成長は,その過程においても到達点においても,本当に国民の生活を豊かにするものであったのかという問いかけの必要性は,戦後51年以降も依然として失われていないのである。
2009年7月31日,原文に加筆・修正のうえ掲載
2010年10月12日,一部修正
(1) Robert W. DeGrasse Jr. Military Expansion Economic Decline New York,1983(藤岡惇訳『アメリカ経済と軍拡』 ミネルヴァ書房,1987年). 本文に戻る
(2) ディグラスの分析に使用された経済統計は,軍事支出は対GDP比,経済成長は実質GDP増加率,生産性は製造業労働生産性上昇率,設備投資は祖固定資本形成の対GDP比. 本文に戻る
(3) 菊本義治『近代経済学と経済政策』大月書店,1993年,109頁。菊本氏はその主張の根拠を示されていないが,ディグラスの図を引用して「図から,軍事支出の少ない国で投資が多く,したがって成長が高いことが読みとれるであろう。軍事費をきめる要因,投資をきめる要因は複雑であるが,軍事費と投資の間にはなんらかの逆相関があるといえそうである」とされている。
ディグラスと同様の見解は,萩原伸次郎氏(『平井規之他編『概説アメリカ経済』有斐閣,1994年,73-74頁)や芦田亘氏(関下稔他編『現代資本主義』有斐閣,1989年,151-152頁)などにも見られる。
本文に戻る
(4) ディグラスは,日,米,英それぞれのデータを除外した分析も行ない,「(軍事支出が経済に悪影響を及ぼすという―延近)われわれの基本的な結論は,1つの国のデータによって左右されなかった」と主張する一方で,「日本を計算から除外した場合には軍事支出と経済成長との逆相関および軍事支出と生産性上昇率との逆相関は消滅する」とも述べている。DeGrasse
Jr, op.cit., Apenddix B, p.180, Table B.7-B.9.本文中で示したように,日米両国を除外すれば,さらに逆相関は見られなくなるのである。本文に戻る
(5) こうした視点から戦後の日本経済を分析した優れた著作として,井村喜代子『現代日本経済論』有斐閣,1993年,新版2000年)がある。本文に戻る
(6) もちろん,アメリカ経済の衰退と恒常的な軍事力増強とは深い関係をもっており,この関係を明らかにするためには,資本主義の歴史的段階変化に関する理論的考察と戦後のアメリカを中心とする資本主義世界体制の構造分析とが不可欠である。
この問題についての参考文献は多数あるが,北原勇『独占資本主義の理論』(有斐閣,1977年),南克己「アメリカ資本主義の歴史的段階」(『土地制度史学』47号,1970年),延近「アメリカの軍事力増強と軍事支出増大の恒常化について」(『三田学会雑誌』82巻1号,1989年,83巻3号,1990年)をあげておく。本文に戻る
この「戦後日本の経済成長の性格」の著作権は慶應義塾大学 経済学部 延近 充が所有します。無断で複製または転載することを禁じます。
Copyright (c) 2009 Mitsuru NOBUCHIKA, Keio University, All rights reserved.
トップページへ(検索サイトからこのページへ来られた方用)