| 新** | 再** | 合計 | |||||||
| 19年 | 18年 | 17年 | 19年 | 18年 | 17年 | 19年 | 18年 | 17年 | |
| S | 4.4 | 4.8 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 4.1 | 4.5 | 7.5 |
| A | 19.6 | 15.0 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 18.2 | 14.3 | 16.5 |
| B | 29.4 | 29.9 | 28.6 | 18.8 | 14.3 | 13.3 | 28.6 | 29.2 | 27.5 |
| C | 32.8 | 31.3 | 29.7 | 43.8 | 14.3 | 26.7 | 33.6 | 30.5 | 29.5 |
| D | 13.7 | 19.0 | 17.8 | 37.5 | 71.4 | 33.3 | 15.5 | 21.4 | 19.0 |
| 受験者 | 204 | 147 | 185 | 16 | 7 | 15 | 220 | 154 | 200 |
| 欠席率 | 3.3 | 7.5 | 17.4 | 30.4 | 53.3 | 55.9 | 6.0 | 11.5 | 22.5 |
| 履修者 | 211 | 159 | 224 | 23 | 15 | 34 | 234 | 174 | 258 |
欠席率は欠席者の履修者に対する%
| * | 評語は,試験の得点(素点)にレポートの得点(15点満点)を加算(評点)し, S,A,B評価はその評価にふさわしい水準の答案であることを原則として, 以下の基準で評価した。 S:素点90点以上,OR評点90点以上AND素点80点以上 A:素点80点以上,OR評点75点以上AND素点65点以上 B:素点60点以上,OR評点60点以上AND素点50点以上 C:素点35点以上,OR評点35点以上AND素点25点以上 D:上記以外 |
| ** | 新は新規履修者,再は再履修者(以下同じ)。 |
| 最高点 | 最低点 | 平均点 | |||||
| 新 | 再 | 新 | 再 | 新 | 再 | 全体 | |
| (1) | 30 | 25 | 0 | 0 | 49.5 | 28.5 | 48.0 |
| 1. | 15 | 15 | 0 | 0 | 54.6 | 32.5 | 53.0 |
| 2. | 15 | 12 | 0 | 0 | 44.5 | 24.6 | 43.1 |
| (2) | 70 | 53 | 0 | 0 | 54.8 | 37.2 | 53.5 |
| 合計 | 100 | 72 | 6 | 0 | 53.2 | 34.6 | 51.9 |
| 前年度 | 88 | 63 | 0 | 16 | 48.8 | 32.4 | 48.1 |
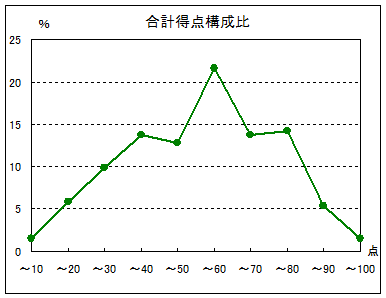
*新規履修者のみ。再履修者は受験者が少なくばらつきが大きいので省略した。
第2図 問題別得点分布(1)
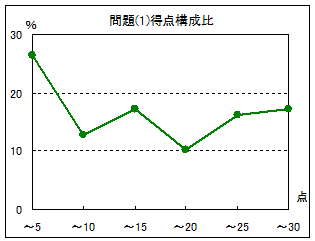
第3図 問題別得点分布(2)①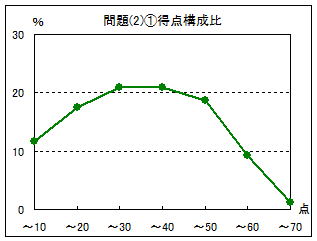 |
第4図 問題別得点分布(2)②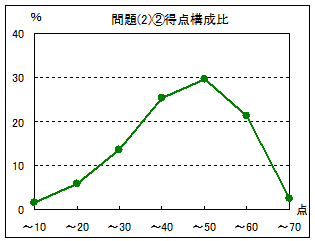 |
問題(1)は2017年度で出題し,問題(2)は,授業内レポートの課題8,9と同じ問題で,2017年度と2018年度でも出題した問題ですから,レポートを自分の力で書き,過去問を解くという努力をしていれば,解答は容易だったのでしょう。ただ,平均点は問題(1)が49.5,問題(2)が54.8と,それほど高くありませんでした。
答案を見ると,その原因は明らかです。過去問の採点基準を持ち込んでいたとしても,箇条書きをそのまま書いても答案にはなりません。内容を理解したうえで文章化するという努力をしたか否かが得点に直結します。
(1)の①では,生産力と生産量の区別ができていない答案や,生産力上昇率で賃金率が上昇すれば,有機的構成は変化しないとすべきところを,ただ賃金が上がれば有機的構成が変化しないという答案が少なくありませんでした。
(1)の②では,労働手段の意味が分からずに労働者の年齢構成と勘違いしている答案は論外としても,「消費手段販売額と等しい固定資本の現物更新が必要」という解答が続出したのは驚きでした。消費手段販売額とはつまりII部門の生産額の意味ですから,まったく意味が異なります。
推測ですが,レベルの低い「模範解答」のようなものが出回り,それを何の疑問もなく答案にそのまま書いたものと思われます。
自分の力で理解し,レポートや答案を書くことが何よりも重要と繰り返してきたのですが・・・。また,個別資本とすべきところを「個人資本」と書いた答案も多かったことも,レベルの低い模範解答の出回りのせいなのでしょう。
これが(1)の平均点が低かった原因です。
(2)の①でも,採点基準の競争的市場の特徴として「価格支配の可能性」とあるのは,個別資本の生産量調整では価格に影響を与えられないこと,多数の資本の価格協定成立が困難なこと,たとえ協定が成立しても参入が容易なために,価格支配は不可能なことを書くべきなのですが,価格支配の可能性があると書いた答案が少なくなかったのです。
(2)の②では,1950年代前半に,朝鮮特需によって獲得した外貨によって合理化投資が行なわれたことに言及するのは妥当なのですが,合理化投資によって,素原料やエネルギー以外の生産手段を国内で生産できる再生産構造が形成されたとすべきところを,「合理化投資によって再生産構造が形成された」という記述が多かったのも,非常にレベルの低い「模範解答」の存在を推測させます。いうまでもなく,たんに「再生産構造が形成された」では,経済学的にまったく無意味な叙述です。
授業でも話しましたが,私は今年度限りで授業担当は終了です。経済学部には,定年退職者が担当していた科目について,専任者に担当できる者がいない場合,3年を限度として退職者に授業の担当を依頼できるという内規があります。
私は今年度が2年目ですが,マルクス経済学の授業担当案を作成する大西広さんから,「2020年度のマルクス経済学と独占資本主義論は専任者で賄うことになりました」という理由で,私に担当を依頼しないとの連絡がありました。
「なりました」と何か学部内の委員会で決まったような表現ですが,理論部会のカリキュラム委員からはそのような決定はされていないという情報をもらいました。それで大西さんにどのような組織で決まったのかを問い合わせると,組織名などの回答はなく,カリキュラム委員会で退職者の授業担当は原則2年にすると決まったとの回答がありました。
これも,カリキュラム委員会でそのような決定ができるわけではないので,これが虚偽であることは明らかです。
マルクス経済学I ,II は大西さんの教え子を非常勤講師として担当させることになったようです。最初の理由と矛盾する担当案ですね。独占資本主義論は大西さんが担当されるようですが,この分野について大西さんに業績があるわけではないので,おそらく大西さんが理論部会で提案され,却下され続けている,独占資本主義論を「マルクス経済学中級」に変更する案を実現するためのフレームアップと推測するしかありません。
事情はともあれ,私は非常勤講師の身分ですから,授業担当案に異議を唱える権限がありませんので,経済学部での授業担当はなくなりました。
にもかかわらず,この講評を書いているのは,学生の皆さんに,この科目に限らず,学習に取り組む姿勢を伝えたいという思いからです。
皆さんに私の思いが伝わって,今後の学習の参考になることを願っています。
| 課題番号 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 合計 |
| 新 | 57.8 | 55.9 | 51.2 | 54.0 | 53.6 | 45.4 |
| 再 | 30.4 | 39.1 | 26.1 | 26.1 | 17.4 | 23.2 |
| 全体 | 55.1 | 54.3 | 48.7 | 51.3 | 50.0 | 43.2 |
| 提出回数 | 5 | 4 | 3 | 2-0 |
| 平均点 | 63.8 | 52.0 | 51.0 | 43.2 |
| レポート評価 | A | B | C | D |
| 平均点 | 71.6 | 57.0 | 51.8 | 42.6 |
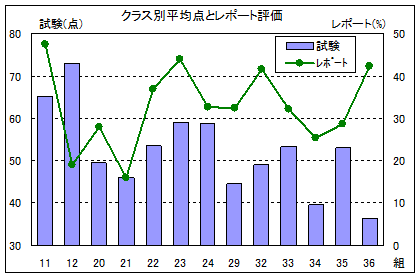
*時間割に指定されたクラスのみで,履修者の極端に少ないクラスは除いた。
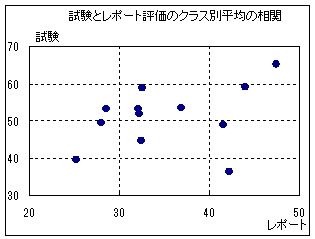
*時間割に指定されたクラスのみで,履修者の極端に少ないクラスは除いた。
授業内容についての感想とともに書かれていたものの一部を,紹介しておきます。
「一年間ありがとうございました。マルクス経済学はなかなかメディアでも取り上げられることが少なく,現在の経済をマルクスで読み取った授業は新鮮でおもしろかったです。今年で退職なさるということで,来年独占資本主義論を取ろうと思っていたので残念です。お体を大事になさってください」
*教科書には独占資本主義論も含まれているので,自習してみてください。わからないところがあれば,メールで質問してくれればできる限り対応します。
「1年間ありがとうございました。残りの人生を楽しんでください!どうか長生きしてください。」
*ありがとう!研究と教育が私の人生の生きがいであり楽しみでした。これからもウェブサイトやその他の方法で私の考えを発信していくつもりです。
「延近先生,教員生活お疲れさまでした。まずはお身体を大事になさってください。入学するまで知らなかったマルクス経済学の学問分野に,多少なりとも触れることができ,非常に有意義でした。時々HPものぞいて,学んだことを今後の自分の専攻に生かしていけるようにしたいと思います。私も癌の治療を頑張りつつ,学業に励む所存です。1年間ありがとうございました。」
*この学生は,ガンを発症し,それが他のの臓器にも転移したために抗ガン剤治療中であることを,メールのやり取りで知りました。休学の可能性もあるとのことでしたが,毎回のレポート提出と定期試験の受験をうれしく思っています。ガンを克服されることを願っています。
「とても授業はわかりやすく,課題を出すことで理解が深まりました。まだ浅い部分しか学べていないので,今後はより詳しく学んでいきたいです。先生の体調がとても心配です。これからも元気でお過ごしください。」
*今までに出版した3冊の本は,私の研究成果として自信を持っています。どうか読んで学んでください。質問があれば対応します。
「長きにわたる教員生活お疲れさまでした。最後の年となる先生の授業を受けることができてよかったです。マルクス経済学は自分が予測していたものとは全く異なりました。資本主義分析を現代にも応用する授業はとても興味深かったです。」
*資本論の文章をああでもない,こうでもないという解釈学は,専門研究者としては必要で,私も若いころにやりましたが,マルクスの分析を基礎としつつ,さらに発展させて現代経済を分析することこそが,私の目標でした。その集大成が3冊の本で,その内容を皆さんに教える機会が与えられてきたこと,そしてそれを興味深いと思ってくれた学生が何人もいることに感謝しています。
「時間がぎりぎりなのであまり長くは書けませんが,毎授業参加したマルクス経済学は,私にとって影響が大きいものでした。必死になって空欄補充していた授業が懐かしいです。先生は20年あまり慶應義塾で教鞭をとられていた(年数定かでありませんが)と伺いましたが,最後の年として先生の授業を聞けたのは光栄でした。やりがいがありためになる授業をありがとうございました。」
*学生を教える立場になってから35年あまり経ちます。4月からどんな生活になるのか,自分でもわかりません。研究は続けていきますが,きっとみんなの前で話をする機会がなくなった喪失感が襲ってくるのでしょうね。
まだまだ感想はたくさんありましたが,最後に。
熱心に授業を聞いてくれたみなさん,私の経済学や余談に興味を持って聞いてくれ,私の身体を気遣ってくれた学生さんがたくさんいたこと,このことは絶対忘れませんし,これからの私の人生にとって力になると確信しています。
ほんとにありがとうございました!!。勉強がんばってね!