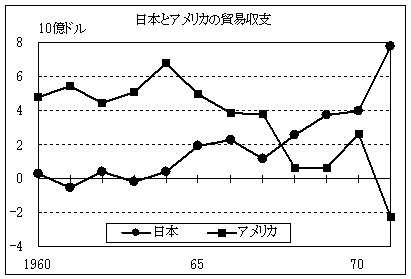
世界的金融・経済危機の構造:試験問題と採点結果
(2015年度)
[問題]以下の(1)〜(3)のうち1問を選んで答えなさい。2問以上に解答した場合は無効とします。答案用紙に記入する際には解答の冒頭に選択した設問の番号を明記すること。
(1) 下のグラフは1960年から1971年までの日米の貿易収支を示したものである。また,日米間の貿易収支は1965年以降,日本の黒字基調となっている。このような変化が起こった理由について,1950年代以降のアメリカの冷戦戦略と日米関係と関連付けて説明しなさい。
- (2) 1980年代に顕著となったアメリカの「双子の赤字」ついて,
- (a) 赤字の1つが90年代に解消された理由を説明しなさい。
(b) 90年代にさらに膨大化したもう1つの赤字はどのようにファイナンスされたか。
(3) 2000年代のブッシュ政権期の景気回復と投機的金融取引の盛行との関係を説明し,この景気回復が2008年の金融・経済危機に帰着する理由を理論的に明らかにしなさい。
以下の内容がどの程度説明されているかによって得点を与えます。絶対評価を基本としますが,相対評価を加味(全員の答案を読んだうえで採点基準・配点を変更)する可能性があります。
(1) アメリカの冷戦戦略と日米経済
- 1.アメリカの冷戦戦略の実行(30点)
- (a) NSC-68の戦略:恒常的軍拡体制の成立
(b) ニュー・ルック戦略:超先端軍需産業の創出・育成
(c) 柔軟反応戦略:対兵力戦略の採用・軍事技術の高度化の追及
(d) ベトナム戦争への本格介入
- 2.アメリカの在来産業の競争力低下(40点)
- (a) アメリカ経済の軍事化
(b) アメリカ企業の多国籍化
(c) 60年代の経済政策とベトナム戦争→景気過熱→物価上昇
- 3.日本の経済復興と高度成長(30点)
- (a) 朝鮮特需:生産手段の国内生産体制
(b) ベトナム戦争:ベトナム周辺諸国へ輸出の急増
(d) アメリカ経済の相対的衰退と日本の国際競争力強化→対米輸出の急増
- (2) 「双子の赤字」
- (a) 90年代の持続的経済成長による税収増大→財政赤字の縮小・黒字化
- 1.持続的成長の諸要因:クリントン政権の政策・IT革命,平和の配当等(40点)
2.個人所得税と法人税の増収:投機的金融取引の盛行(10点)
- (b) 90年代の経常赤字のファイナンス構造
- 1.グローバルな生産体制のもとでの貿易赤字累増体質の深化(10点)
2.アメリカをハブとするグローバルで大規模な資本取引循環(20点)
3.投機的金融取引増大に依存した経常赤字のファイナンス構造(20点)
(3) ブッシュ政権期の景気回復のメカニズムとその限界
- 1.ブッシュ政権の景気対策:住宅投資推進策(10点)
- 2.サブプライム・ローンと投機的取引の拡大:「債権の証券化」と「証券の証券化」(20点)
- 3.住宅価格上昇と個人消費の増大:ホーム・エクイティ・ローンやキャッシュアウト・リファイナンスの利用増大(20点)
- 4.住宅価格上昇に依存した景気上昇と投機的取引の限界(50点)
- (a) 証券化商品によるリスク・ヘッジの理論の誤謬
(b) 住宅価格上昇の限界
(c) 住宅売却による債権回収の限界
⇒住宅価格上昇と個人消費増大に依存した景気上昇の限界
採点と成績集計が終わりましたので成績統計とコメントを掲載しました(7/28)。
|
第1図 得点分布*(各得点階層が受験者総数に占める割合)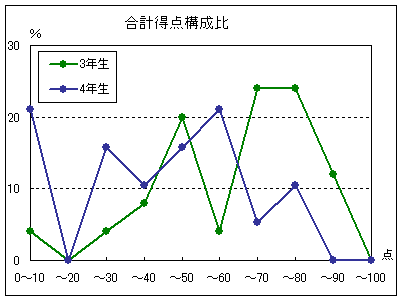 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3表 レポート提出率(%)
|
第4表 レポート提出と平均点の相関
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメント 15年度は3つの問題から1つを選択して答える形式としました。3問ともこの講義のエッセンスとも言うべき論点に関するものですが,履修者の興味や理解度に応じて答えられるようにしたわけです。いずれも授業内レポートの課題に即した問題でしたから,授業に出席し講義資料でノートをとって授業内レポートを提出し,論述ポイントで復習していれば,平易な問題だったはずです。それらが不充分だったとしても,持ち込み可ですから,試験前に授業内レポートの課題を論述ポイントにしたがって教科書で勉強していれば解答は充分可能だったはずです。 3年生のA評価が56%と好成績だったのはこれが理由でしょう。ただし,平均点は61.6で14年度に比べれば2ポイント上がったものの,A評価が過半数であるにもかかわらず,それほど高くはありません。これは,D評価が12%と昨年度までに比べて多くなり,第1図の得点分布が示すように,その得点も非常に低かったのが原因です。4年生のA評価は10.5%と昨年度までより減少,D評価は36.8%と増加しています。平均点は54.4で3年生より10ポイントも低くなっています。 3年生・4年生ともに平均点が低く,D評価が増加した理由は,第3表と第4表で明らかになっています。レポート提出率は3年生64.1%,4年生27.6%で,14年度の73.9%,31.0%より低下しています。そしてレポート提出と試験の平均点の間には明確な正の相関があります。D評価はレポート提出回数が2回以下に限られており,その大部分が提出ゼロ回です。 上に書いたように,D評価の学生はレポート提出を怠っただけでなく,レポート課題を教科書で勉強するという最低限の努力も怠ったのでしょう。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||